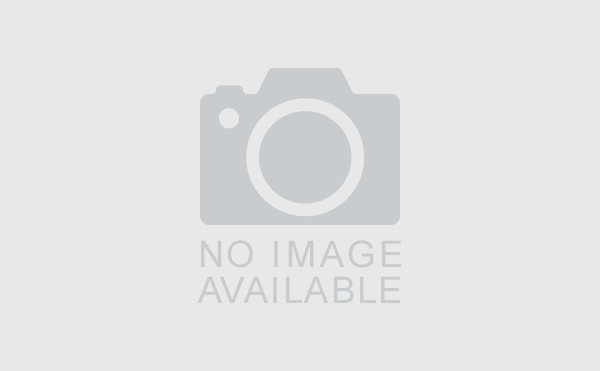勉強効率を上げる「インターリーブ学習法」とは?
「たくさん勉強しているのに、なかなか成績が上がらない…」
そんな悩みを持っている人におすすめなのが、「インターリーブ学習法」です。
この学習法は、同じ科目や問題を繰り返す「ブロック学習」とは異なり、異なる科目や種類の問題を組み合わせて学習する方法です。スポーツのトレーニングや芸術の分野でも使われている、効果的な学習法の一つです。
1. インターリーブ学習法とは?
インターリーブ(Interleaving)とは、「交互にする」「入れ替える」という意味です。
例えば、数学の勉強をするときに、
✅ ブロック学習:同じ問題形式を連続で解く(例:二次関数の問題ばかり解く)
✅ インターリーブ学習:異なる種類の問題を交互に解く(例:二次関数・確率・図形の問題を混ぜて解く)
このように、1つの分野に偏らずに学習を進めることで、柔軟な思考力や応用力が鍛えられます。
2. なぜインターリーブ学習が効果的なのか?
インターリーブ学習が効果的な理由はいくつかあります。
① 思い出す力が強化される
同じ種類の問題ばかり解いていると、「解き方を覚えているだけ」になりがちです。しかし、異なる問題を交互に解くことで、「これはどの解法を使えばいいのか?」と考える機会が増え、記憶の定着が促されます。
② 本番に強くなる
試験では、同じ形式の問題が連続して出るとは限りません。いろいろな種類の問題に対応できる力をつけることで、実際のテストでも柔軟に対応できるようになります。
③ 飽きにくく、モチベーションが続く
同じことばかりしていると、飽きてしまうこともありますよね。インターリーブ学習なら、違う種類の問題を切り替えながら進めるため、飽きずに集中力を維持しやすくなります。
3. インターリーブ学習の実践方法
インターリーブ学習を取り入れるには、以下のような方法が効果的です。
✅ 科目を交互に勉強する
例:数学を30分勉強したら、次は英語を30分、その後また数学に戻る
✅ 異なる種類の問題を混ぜる
例:数学なら「二次関数→確率→図形→整数問題」のようにランダムに解く
✅ 過去問を使う
試験の問題は基本的にインターリーブ形式なので、実際の試験問題を解くこと自体がよいトレーニングになる
✅ アプリを活用する
ポチがくなどの勉強アプリを使い、ランダムな問題を解くことでインターリーブ学習が自然にできる
4. まとめ
インターリーブ学習法は、単調な「繰り返し学習」よりも記憶の定着率が高まり、応用力がつく学習法です。最初は少し大変に感じるかもしれませんが、続けることで確実に効果を実感できるはずです。
「勉強してもなかなか身につかない」と感じている人は、ぜひインターリーブ学習を試してみてください!